【簡単まとめ】食品ロスについて

今回は食品ロスの問題について少し書いてみようと思います。
皆さんも食品ロスが問題となっていることについて一度は耳にしたことがあると思いますし、
プラスチックの問題と同様に私たちにとってとても身近な問題であると思います。
この食品ロスとはどういう問題であるのかを簡単に書いてみたので、
この記事を読んで皆さんにもより知っていただけたら嬉しいです。
食品ロスとは?
食品ロスとは、食品が本来食べられるものであるのに捨てられてしまうことをいいます。
日本では食品を食べられる部分(可食部と呼ぶ)と食べられない部分(不可食部)に分け、
可食部で捨てられている食品を食品ロスとしています。
皆さんもイメージできると思いますが、
例えば、ニンジンの皮や魚の内臓や骨であるとか、加工や調理の中で発生する野菜、果物の皮や芯または種、肉、魚の骨やアラといった食品のなかでも食用とできないものが不可食部となります。
これらは食品ロスとは呼ばれません。
一方、食べられたはずの部分であるのに、傷んだものや過剰に除去されたものは可食部であり、
食べ残しによる廃棄などと同様に食品ロスとされます。
食品ロスはどれくらい出ているのか?
では、日本ではどれくらいの食品ロスが出ているかについてですが、
農林水産省の平成30年度の推計値で日本の食品廃棄物は年2,351万トンと出されています。
その中でも先ほど説明した本来食べられるものであるのに捨てられている食品である
食品ロスは年およそ600万トン出されています。
この食品ロスは事業によって出される食品ロスの「事業系食品ロス」と
各家庭から出されるものの「家庭系食品ロス」の二つに分けることができます。
二つに分けた数字も農林水産省から出されていますが、
事業系の食品ロスが324万トン、一方家庭からのものが276万トンとされています。

ここで注目すべきは家庭から出ている食品ロスではないでしょうか。
コンビニの恵方巻の売れ残りが大量に廃棄されるみたいな食品ロスに関するニュースをみたことがありますが、そういうこともあって割合的に事業系によるものが多いというイメージがあったたのですが、家庭からもこれだけ出ているというのは意外というか少し驚きでした。
なぜ食品ロスは環境問題となるのか?
この食品ロスが問題となるのは、本来食べられたはずであるのに食べられずに捨ててしまわれていることで食品を無駄にしている、もったいないという倫理観のことに加えて環境にも悪影響を与えるということです。
食品ロスが増えれば、食品廃棄物を処理する過程で必要となるエネルギーや
発生する二酸化炭素などの温室効果ガスを増やすことになります。
食品廃棄物に関する温室効果ガスの排出量は思いの外大きく、
世界全体の食品廃棄物による温室効果ガスの排出量では、
ロシアや日本一国の排出量よりも多くなっているのです。
そして、食料生産には水や土地などの資源が当然必要になりますが、
食べられる食品を捨てることは、そうして作られた食料に使われた資源も無駄にしてしまうことになります。食品ロスを増やすことで、限りある地球の資源も無駄にしてしまっているのです。
食品ロスによる温室効果ガスの排出などの環境への影響についてはまた別の記事でより詳しく書けたらと考えています。
この食品ロスの問題については、私もとても関心のあるテーマなので
その環境への影響や世界で行われている食品ロスを減らす取り組み、
また食品ロスを減らすために私たちでもできることなど、
これからもまた記事を書いていきたいと思っています。
参考文献
国際農林業協働協会(JAICAF)(2014)「食料のロス・廃棄が環境に与える影響」『世界の農林水産』835:03-08 www.fao.org/3/b-i4659o.pdf
農林水産省ホームページ https://www.maff.go.jp/(2021年7月21日閲覧)
-
前の記事
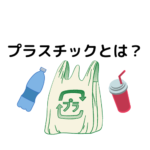
プラスチックとは?プラスチックとは何かを調べてみました! 2021.07.21
-
次の記事

「プラスチックとは?」プラスチックの種類をまとめてみました 2021.07.25
