プラスチックとは?プラスチックとは何かを調べてみました!
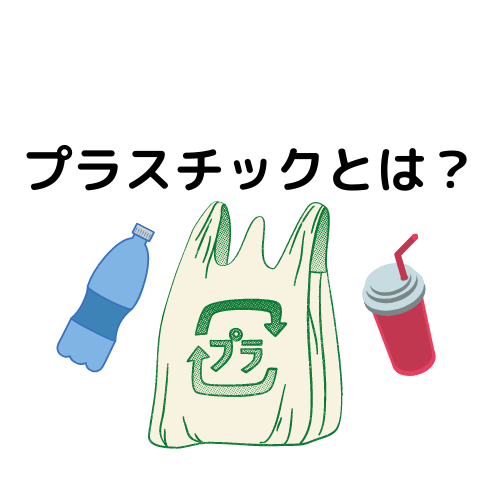
プラスチックってどんなもの?
プラスチックってどういう定義?
前回の記事でプラスチックがなぜ環境に悪いのかを簡単に解説しましたが、
じゃあそのプラスチックって何?どういう定義?というのを私もうまく説明することができないなと感じたので、
今回はそもそもプラスチックとは何か?ということを一緒に学んでいけたらと思います。
プラスチックの定義
そもそもプラスチックとはどんなものを表す言葉なのだろうということで、
まずはじめにプラスチックの定義を調べてみました。
JIS K 6900には、名詞としてのプラスチックの定義は
「必須の構成成分として高重合体を含みかつ完成製品への加工のある段階で流れによって形を与え得る材料。」
とありました。
難しい言葉があって何を言っているのだろうとなってしまいましたが、
高重合体なるものを含んでつくられた材料がプラスチックであることになると思います。
では、その高重合体というものは何であるのかというのがさっぱりわからないので、辞書を引いて調べてみました。
広辞苑で見てみたところ「高重合体」とは、重合度の大きい,すなわち重合した単量体の数の多い重合体。
そして「重合体」とは、二つ以上の単量体が重合反応してできた化合物。ポリマー。と出てきました。
ここでポリマーという言葉が出てきました。
なるほど!重合体とはつまりポリマーのことだったんですね。
ポリマーという言葉は何となく聞いたことがありそうだけど、全く何かわからない……。
となったので今度はポリマーを調べてみました。
「ポリマー」とは化学用語で、より小さな単位分子である「モノマー」の重合体、
つまりモノマーが結合したものことをいいます。
モノマーとはガスや液体の形で小さな分子が集まったものことです。
例えば、プラスチックの種類でポリエチレンというものがありますが、
エチレンとはモノマーの一種であり、
このモノマーをつなげるとポリエチレンというポリマーとなり、
つまりプラスチックとなるというわけです。
ちなみに、このポリマーには「天然」と「合成」のものがあります。
天然ポリマーは、自然界に存在するセルロースや天然ゴムなどがあります。
また、人体の筋肉や皮膚を構成するたんぱく質、DNAも天然ポリマーです。
一方、化石原料などから化学的に合成されたもの、つまり人工的につくられたものが合成ポリマーです。
この合成ポリマーに広く含まれるのがプラスチックとなります。
ここまでくると、ポリマーがプラスチックであるということを理解することができました。
少しわかりづらい説明になってしまいましたが、皆さんも理解してくれましたでしょうか。
プラスチックの語源
さてこのプラスチック(Plastic)の語源ですが、
ギリシャ語の形容詞「plastikos」が語源だと言われています。
この言葉は「形づくる」といった意味があり、
可塑性を表す形容詞などとしても使われていたそうです。
日本語に言い換えるとするならば、プラスチックとは一般に可塑性物質という意味になります。
「可塑性」とは、力を加えると変形し、その力を除いても形状が保たれる性質のことを指しています。
プラスチックの性質
皆さんの周りでも柔らかくて変形できるプラスチックや、
その一方固くて丈夫なプラスチックもすぐに見つけることができると思いますが、
こうした様々な硬質や形状をつくることができるのがプラスチックの特徴となります。
柔らかいプラスチックとなったり固いものとなったり、
そのようなプラスチックの性質を決めているのがポリマーの長さと配置の構造です。
ぎっしり詰まった密度の高いポリマーであると固いプラスチックに、
反対に隙間が多く密度の低いポリマーは柔らかいプラスチックになるといった具合です。
ただし、ポリマー単体では実用的な価値をもたせることはできないので、
ここに添加剤が加えられることになります。
着色剤、硬化剤、発泡剤等々求める特性に応じてこれらの様々な添加剤を加えたものが
私たちが普段使うプラスチックとなるのです。
例えば、ビスフェノールAとフタル酸エステルという添加剤をプラスチックの素材に加えることで、
水に強く、燃えにくいという性質を持ったプラスチックをつくることができるようになります。
プラスチックの歴史
今では私たちの生活のあるゆるところで使われているプラスチックですが、
プラスチックがつくられるようになったのはいつ頃からでしょうか。
最初のプラスチックが発明されたのは1869年のことです。
アメリカのジョン・W・ハイアットという印刷業を営む人物が、
セルロースを原料に紙のように薄く伸ばしたり、成型することができる
「セルロイド」という物質をつくり出すことに成功しました。
天然素材を使わない合成ポリマーからつくられたプラスチックが開発されたのは1907年のことです。
人工的につくられたこのプラスチックはアメリカの化学者レオ・ベークライトによって開発され、
開発した彼の名をとって「ベークライト」と名づけられました。
その後、各国でプラスチック開発の研究は進み、
現代使われている様々なプラスチックが次々と開発されていきました。
そして第二次世界大戦後、軽量で耐久性があり、様々な形に成型することができるプラスチックは、
様々な分野の幅広い製品に使われるようになっていき、その生産が急速に拡大していったのです。
説明だけで少し長くなってしまうと思うので、今回の記事はここまでにします。
私もプラスチックとは何かというのをしっかりと理解することができました。
まだ人に説明するのは難しいかもしれませんが……。
「プラスチックにはどんな種類があるのか」などプラスチックについては、
また続きを書こうと思いますのでよろしくお願いします!
参考文献
「プラスチックフリー生活 今すぐできる小さな革命」(著)シャンタル・プラモンドン,ジェイ・シンハ (訳)服部雄一郎 NHK出版 2019年
-
前の記事

【簡単解説】「プラスチックはなぜ環境に悪いと言われるのか?」まとめてみました 2021.07.19
-
次の記事

【簡単まとめ】食品ロスについて 2021.07.23
